日本人の考え方に悩む技能実習生【ミッケル研修】
- ミッケルアート編集部
- 2025年5月6日
- 読了時間: 3分

今回は、日本人の考え方に悩んでいた2年目技能実習生のVさんの事例をご紹介します。
地域 :埼玉県
施設形態:ユニット型特養
研修内容:FUJIYAMA研修
受講者 :ユニット型特別養護老人ホームで2年目の介護職、Vさん
【目次】
はじめに
「食事はいらない」と言われた時の対応
研修での気づき
日本人の考え方に対する意識の変化
施設長からのメッセージ
1. はじめに
技能実習生として2年目になるVさんは、利用者様の声を大切にしながら日々のケアに努めています。そのため利用者様が「食事はいらない」と言ったときにはその言葉を鵜呑みにしてしまい、食事を片付けてしまいました。先輩介護士から「工夫してください」と注意され、悩んでいました。
2. 「食事はいらない」と言われた時の対応
Q. 研修受講前の課題について、どのように感じていましたか?
利用者様に食事を配膳した際、「食事はいらない」と言われ、そのまま片付けてしまいました。利用者様の「食べたくない」という思いを尊重したからです。「食べたくない」の裏にある理由を考えることをおろそかにし、今思えば介護士としての働きは不十分でした。
3. 研修での気づき
Q. 研修でどのような気づきを得ましたか?
利用者様が「食事はいらない」と言ったときには、その背景を探り、解決策を見つけることが重要だと学びました。例えば食べやすい硬さにする、食具を工夫するなどです。食事は生活に欠かせないので、すぐに片付けてはいけなかったのだと反省しました。
4. 日本人の考え方に対する意識の変化
Q. 研修後、あなたの行動はどのように変化しましたか?
「食事はいらない」と言われたら食べ物、食具、時間のタイミングなどさまざまな面から利用者様の背景を探り、なぜなのかを考えるようにしています。関わりを工夫することで、食事をしてもらえることができたときにはホッとします。今後も利用者様の発言の裏側を考えられるようにしていきたいです。
5. 施設長からのメッセージ
介護現場では、利用者様が「食事はいらない」と言う場面があります。この言葉をそのまま受け取ると、必要なケアを提供できないリスクがありますが、技能実習生にとっては日本語の曖昧な表現の背景を理解することが難しく、誤解につながることがあります。利用者様が本当に食事を拒否しているのか、体調不良や気分の問題、遠慮などが背景にあるのかを探ることで、適切な対応が可能になります。これを理解し対応することは、介護施設の経営面でも大きなメリットをもたらします。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。
記事の内容が「いいなあ」と思ったら、いいね(ハート)、メルマガ登録、社内共有をお願いします。
メルマガでは、施設運営やケアに役立つ情報などが無料でお届けします。
皆様の施設の次世代リーダーを応援します!
\もっと詳しく知りたい方はこちら/
%203%202.png)






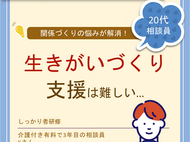




コメント