会話が一方的になってしまう【ミッケル研修】
- ミッケルアート編集部
- 2025年5月6日
- 読了時間: 3分
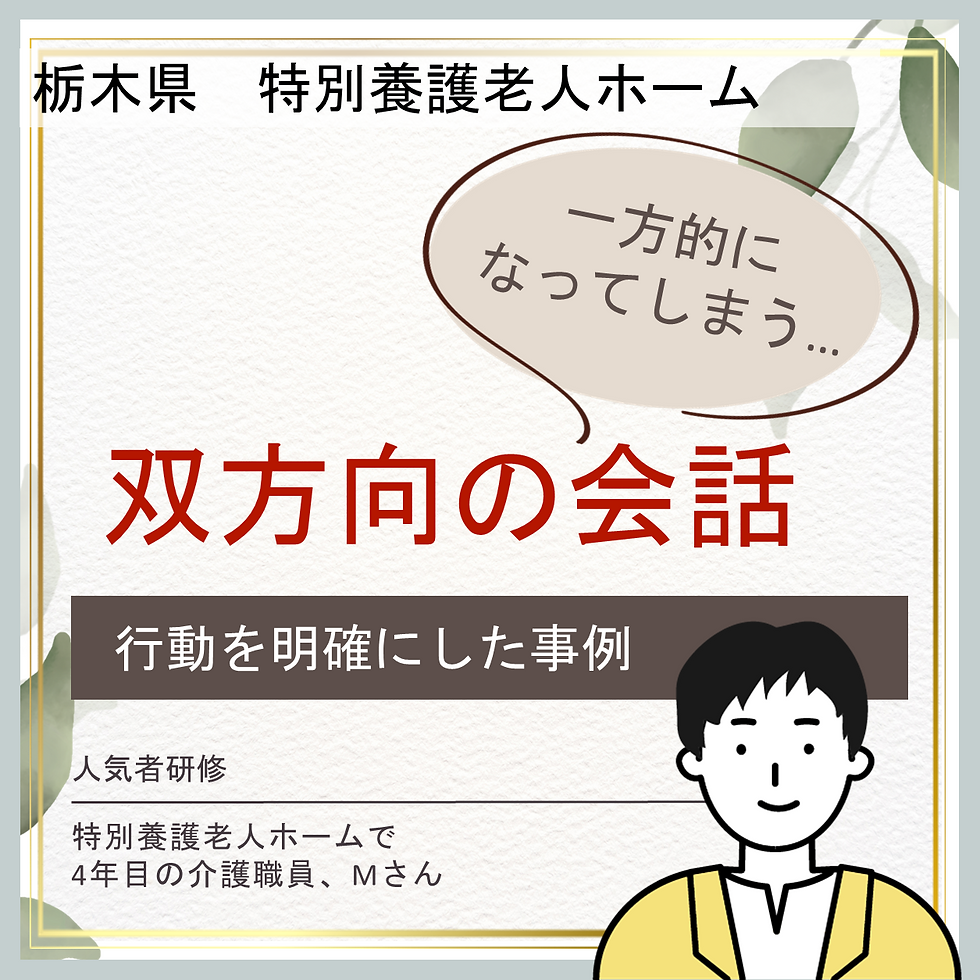
今回は、双方向の会話に苦労していた4年目介護職員のMさんの事例をご紹介します。
地域 :栃木県
施設形態:特別養護老人ホーム
研修内容:人気者研修
受講者 :特別養護老人ホームで4年目の介護職員、Mさん
【目次】
はじめに
声かけに関する苦手意識
研修での気づき
行動計画
声かけに対する意識の変化
専務理事からのメッセージ
1. はじめに
Mさんは特別養護老人ホームで働いて4年の介護職員です。ときどき、自分の話し方が利用者様の考えを尊重できているか不安に感じたり、利用者様の意に反することに誘導するような声かけになっているのではと悩んだりしていました。
2. 声かけに関する苦手意識
Q. 利用者様に声かけをする上で、どんなことが課題だと感じていましたか?
食事介助の際に、利用者様の好みを確認せずに「これを食べましょう」と一方的に勧めてしまったことがありました。時間的制約もある中で、ご利用者の思いを大切にするには、どうしたらいいか考えていました。
3. 研修での気づき
Q. 人気者研修でどのような気づきを得ましたか?
利用者様の立場に立って考えると、どのような言葉づかいや声かけが喜ばれるかが自然とわかるようになりました。また、利用者様の中には聞き上手な方や気配りが得意な方も多く、そのような長所を見習い、お手本にしていきたいと思いました。
4. 行動計画
Q. 具体的にどのようなことを実践しましたか?
「AとB、どちらにしますか」と選択肢を提示して尋ねたり、「ちょっと待ってください」を「あと○分で行きますね」と言い換えたりしています。答えに困っている場合は「はい」「いいえ」で答えられる質問に変えるなど、柔軟に対応できるようになりました。
5. 声かけに対する意識の変化
Q. 研修後、あなたの行動はどのように変化しましたか?
朝のお声がけでは、通勤時に見た街の景色など、興味を持っていただけそうな話題を提供し、反応を見ながら話を広げています。また、服薬指導の前には体調の変化を尋ね、利用者様のサインを見逃さないようになりました。
6. 専務理事からのメッセージ
Mさんは研修を通じ実践的な会話スキルを身につける中で、利用者様の魅力にも気づくことができました。気遣いは介護の根幹であり、職員間の関係性や、将来的には外国人ケア労働者を含む多文化共生の点からも重要です。今後も対話を重ね、周囲の人たちの新たな一面を発見してほしいと思います。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。
記事の内容が「いいなあ」と思ったら、いいね(ハート)、メルマガ登録、社内共有をお願いします。
メルマガでは、施設運営やケアに役立つ情報などが無料でお届けします。
皆様の施設の次世代リーダーを応援します!
\もっと詳しく知りたい方はこちら/
%203%202.png)






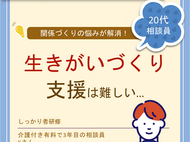




コメント